「アジア最後のアジア」そんな言葉に引かれて、先日会社の仲間みんなとラオスに社員旅行と称して行ってきた。

現地通貨(ラオスキープ)への両替と情報収集はまず最初にやるべきこと。
冒険の始まり感がしていつもワクワクする。
冒険の始まり感がしていつもワクワクする。

日中は30度近くあったので、
毎日たくさん飲んだラオスのビール。
毎日たくさん飲んだラオスのビール。
僕達が行ったのはルアンパバーンとバンビエンという町で、この2つは全く違う魅力に満ち溢れていた。最初に立ち寄ったのは町全体が世界遺産になっている古都ルアンパバーン。ここは仏教的厳かさと市民の暮らしがおり混ざった不思議な空気感を持っていた。

メコン川では、観光船と共にいつも漁が行われていた。

漁で捕れた魚たちは、毎日朝市に並ぶ。大量の魚たちが、朝市が終わる頃には毎回完売していた。
旅のはじめに向かうべきは市場。市場に行けば、人々の暮らしの全てが覗けるので、僕はなるべく行くようにしている。市場にはこの国の人がどんな服をいくらで買い、どんな文房具を使い、どんな食べ物を食べているのかなどが一目でわかるのが面白い。
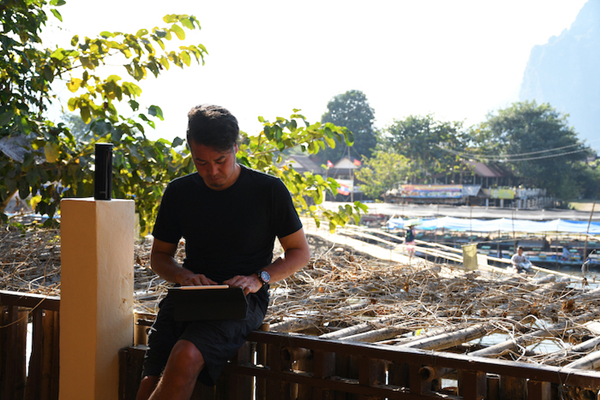
旅の合間に休憩がてらお仕事もする。
疲れた胃には、日本から持ち込んだ温かい日本茶が胃に染み入った。

町中にある配電盤にはDIY感の強さに毎回驚かされた。

よく食べた麺類には、ちぎって入れるたくさんの野菜がついてくる。
レタスにライム、そしてミントが僕の中では新鮮だった。
レタスにライム、そしてミントが僕の中では新鮮だった。

町のカフェは、世界に先んじて?使い捨てない竹のストローが使われていた。
市場の中ではラオスの小さな日常の出来事がたくさん起きている。ある場所ではお店のお母さんたちが井戸端会議をおこない、またある場所では壊れた時計を直す青空時計店に自分の時計の修理は可能かどうかの確認後、お互いスマホを見せ合いながら何やら楽しそうな会話がされている。

市場の文房具店。色々なペンがごちゃごちゃに陳列されていた。
ちなみに5000キープはおよそ60円。

青空時計修理店にはたくさんのお客さんがやってきていた。
物が大切にされているのを感じる。
泣いている子供がいれば親でなくても大人が声をかけ、そしてなだめ、親の元に連れて行ってあげるという、今の日本ではなかなか見られないステキなコミュニティーも見られた。

市場の寂しげな少女には、たくさんの大人が声をかけていた。
市場でラオスの感覚を少し得たところで、街の巡回が始まる。安宿街を抜け、怪しい両替所で高レートの現地通貨に両替をして、町に立ち並ぶサンドイッチ屋さんでサンドイッチを道端でほおばる。サンドイッチは、その昔フランス領だったこともありフランスパン風のパン自体が美味しく、現地の野菜や肉が挟まることでその旨さをいっそう引き上げてくれた。

何度でも食べたかったラオスのサンドイッチ。ベトナムもそうだったが、日本で食べても絶対にうまいクオリティーでおよそ180円

食べ物が旨い理由は市場の野菜の新鮮さのおかげだろうな。
朝は仏教徒が多いラオスならではの托鉢(たくはつ)の時間が流れる。日常的に仏様のために尽くしてくれているお坊さんが、お寺ごとのグループで街を歩き、炊いたもち米やお金、生活に必要なものを街の人からお裾分けをしてもらいながら歩く。街の人はお礼の気持ちを込めてお坊さんにお裾分けをする。「損得」という表現はあまりにも場違いだが、この精神的なウィンウィンの関係は忘れかけていたないか大切なものを感じた気がする。

托鉢の時間中の町は、僕にとっても静かで、そしてなんだかとても大切な時間でした。
流れている時間は世界中同じでも、いつも分単位で動いている僕に(きっとみなさんも)とっては緩やかで、そして穏やかな時間が流れていく。海外旅行というよりも、この時間の流れを再び自分の体の中に流し込めることの贅沢さを感じながら数日が過ぎていった。
次回はラオスのアクティビティー編をみなさんに共有させていただきたいなと思っています。





この記事へのコメント
おこめ
行ってみたいです
ぽんで
メコン川、美しいんだろうな
ほな
メコン川なんて懐かしい。
ほな
日本の昭和時代のようです。